散歩中に、愛犬がおしっこをしたあとにペットボトルの水をかけている飼い主さんを見かけたことはありませんか?
いわゆる「マナー水」ですが、最近では
「本当に意味があるのかな?」
「むしろ広げてるだけでじゃない?」
と感じている人も多いようです。
たしかに、マナー水には限界があります。でも、やらないよりはずっと良いのも事実。
この記事では、マナー水の効果と注意点、そして飼い主ができる工夫についてまとめてみました。
マナー水をかける意味と効果

犬のおしっこは、人間のものよりも濃度が高く、においが強いのが特徴です。
放置すると時間が経つほどアンモニア臭が立ちこめ、特に夏場は不快感が増しますよね。
そこでマナー水をかけると、次のような効果が期待できます。
においをやわらげる
おしっこに水をかけることでアンモニアの濃度を薄めることができます。
ただし、少量ではあまり意味がなく、ある程度しっかりかけることがポイントです。
見た目をきれいに保つ
アスファルトや電柱に残る黄色い跡は、見た目にもあまり気持ちのいいものではありません。
水をかけておくだけでも、通りがかりの人に与える印象はずいぶん違うものになります。
周囲への思いやりの気持ちが伝わる
「きちんと処理している」という行動そのものが、飼い主のマナー意識の表れになります。
犬を飼っていない人にも、安心感を与えられる大切なポイントです。
マナー水の限界と注意点

しかしこの「マナー水」にも限界はあります。
広がってしまうことがある
水をかけることで、おしっこが広範囲に広がってしまうケースもあります。
特に地面が土や砂の場合、すぐに吸収されてしまい、実際にはあまり効果がありません。
においが完全に消えるわけではない
水で薄めても、においを完全に消すことはできません。
とくに同じ場所で繰り返しされると、臭いやシミが残る原因になります。
手間や荷物が増える
毎回ペットボトルを持ち歩くのは意外と手間です。
また夏の暑い時期には、持っている水がぬるくなって衛生的にも気になるところです。
飼い主としてできる工夫

マナー水は「最低限のマナー」ではありますが、それだけでは不十分なこともあります。
日頃から次のような工夫をしておくと、より快適に散歩ができます。
散歩前に排泄を済ませる
我が家でも実践している方法ですが、家を出る前にトイレを済ませておくと外での排泄回数が減ります。
「おしっこしてからお散歩に行こうね」と声をかけて習慣化すると、自然と身につきます。
パピーの頃から続けてきたおかげで、外出先でも「ここではしない」という区別がついています。
お店やカフェでも安心して過ごせるのは、このトレーニングの成果だと感じています。
消臭効果のあるマナー水を使う
最近では、ペット専用の消臭スプレーや希釈液も多く販売されています。
ただの水よりもにおいを抑えられるうえ、植物や土にもやさしい成分のものが多いです。
吸水シートやティッシュを持参する
水をかける前に、おしっこを吸水シートやティッシュで吸い取ると広がりを防げます。
私は薄手のトイレシートを小さくカットして、いつもお散歩バッグに数枚入れています。
うんち処理のときにも使えるので、とても便利です。
排泄の場所を選ぶ
電柱・建物の壁・玄関前などは避け、なるべく草地や地面の柔らかい場所で排泄させましょう。
これだけでも、においトラブルや近隣との摩擦をかなり防ぐことができます。
まとめ|大切なのは「思いやりの心」
犬の散歩中のマナー水には、
においをやわらげる・見た目をきれいにする・思いやりを伝える
といった効果があります。
ただし、水をかけるだけでは十分ではなく、飼い主の意識や工夫が欠かせません。
マナー水を使うこと自体が目的ではなく、
「まわりの人も気持ちよく過ごせるように」という心遣い。
それが、犬と暮らす私たちにとっていちばん大切なマナーなのかもしれませんね。もありますが、結局は「飼い主の心配り」ではないでしょうか。犬と暮らす飼い主同士が互いに気持ちよく散歩できるように、日々のマナーを意識していきたいですね。
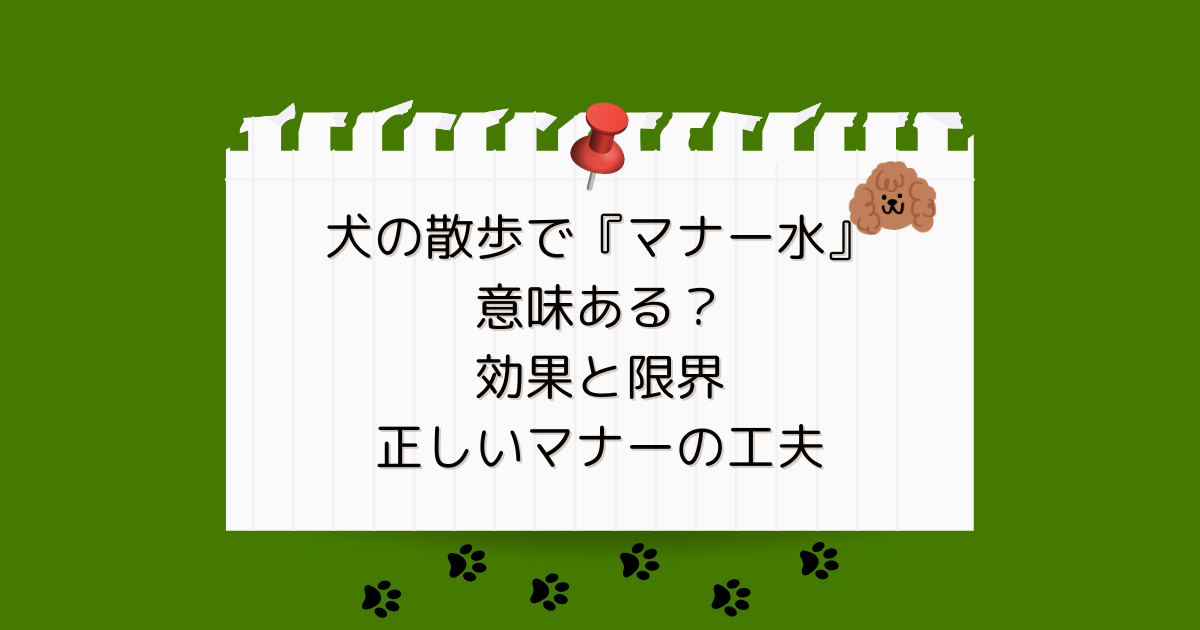
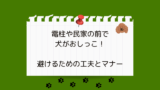


コメント